
バッハ:ヴァイオリン・ソナタ集
この演奏で最も注目すべき点は、ソロを弾くラインホルト・バルヒェットが飾り気のない、すこぶる流麗でシンプルな解釈を示していることで、これによってバッハの書法が真摯に再現されている。モダン奏法によるバルヒェットのヴァイオリンとチェンバロによるセッションだが、聴き込んでいくと装飾音の扱いなどからバルヒェットがいかに古楽を良く研究していたかが理解できる。当時まだ古楽の黎明期にあって、本来のバッハの音楽表現に相応しい演奏を試みている稀なヴァイオリン・ソナタ集だ。ヴァイオリンの大家が弾く、風格はあるがバロックの室内楽としての魅力からはいくらか乖離した演奏とは異なり、モダン奏法によるバッハの音楽に対する無理のない再現と、その両立にも成功している例ではないだろうか。それは良い意味での中庸の美で、古楽がピリオド楽器及びピリオド奏法によって演奏されることが当然になった現在では、得難いサンプルとしての価値を持っている。バルヒェットのソロに花を添えているのがヴェイロン=ラクロワのチェンバロで、その軽妙洒脱な奏法がこの曲集をより親しみ易いものにしている。このセッションで彼が使用しているのはクルト・ヴィットマイヤー製作のモダン・チェンバロで、確かにピリオド楽器に慣れた耳には時折音色が厚かましく感じられることがあるにせよ、彼はレジスターを巧みに操作して楽器の弱点をカバーしている。
個人的に話になるが、私が高校生の頃、毎週日曜日の朝NHK.FMから放送されていた角倉一郎氏の解説による『バッハ連続演奏』というラジオ番組があって、ある時彼がこの演奏を採り上げていた。それがこの録音を知った最初の体験で、今でも印象深く記憶に残っている。エラート音源の3枚組のLPは、その後長い間廃盤の憂き目に遭っていたが、一度日本でCD化され更に2009年にワーナー・ミュージックとタワー・レコードのコラボによってデトゥール・コレクションのひとつとして2枚組の廉価盤で復活したものがこのセットだ。なお偽作を含む通奏低音付のBWV1021から1024の4曲のソナタではチェロのヤコバ・ムッケルが参加している。録音は1960年頃という表示があり、現代ピッチのa'=440Hzを採用している。
個人的に話になるが、私が高校生の頃、毎週日曜日の朝NHK.FMから放送されていた角倉一郎氏の解説による『バッハ連続演奏』というラジオ番組があって、ある時彼がこの演奏を採り上げていた。それがこの録音を知った最初の体験で、今でも印象深く記憶に残っている。エラート音源の3枚組のLPは、その後長い間廃盤の憂き目に遭っていたが、一度日本でCD化され更に2009年にワーナー・ミュージックとタワー・レコードのコラボによってデトゥール・コレクションのひとつとして2枚組の廉価盤で復活したものがこのセットだ。なお偽作を含む通奏低音付のBWV1021から1024の4曲のソナタではチェロのヤコバ・ムッケルが参加している。録音は1960年頃という表示があり、現代ピッチのa'=440Hzを採用している。
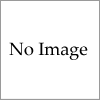
バッハ:ヴァイオリン・ソナタ集
バッハのヴァイオリンソナタ曲集は、当然たくさんのレコーディングが発表されており、自分の尊敬するあるいは好みの演奏家の録音作品があれば、それを聴くに如くはない。
とはいいつつも、ヴァイオリンはよく知らないけどマァ聴いてみようか、というスタンスの人や、既に誰かの録音作品を持っているが違う演奏も聴いてみたいという人には、全曲演奏であることや、プライス的な面も含めて、本作品は無難な選択といえると思う。
曲群としては2つめのト長調が、割と有名ではないか?
あとは、1枚目の11トラックの、チェロとの2重奏が、切々としていて訴えるものがある。私には、全曲中でもっとも印象に残る出色の名演に聴こえる。
バルヒェットの演奏において、たとえば解釈の斬新さとか、そういったものがあるのかどうかは、ちょっとわからないが、私はオーソドックスな演奏という印象を受ける。
なお、伴奏はチェンバロであり、全体としてボトムが軽くなる感じはあるものの、ヴァイオリン自体が中域から高域に特徴があるためか、それほど気にはならない。
とはいいつつも、ヴァイオリンはよく知らないけどマァ聴いてみようか、というスタンスの人や、既に誰かの録音作品を持っているが違う演奏も聴いてみたいという人には、全曲演奏であることや、プライス的な面も含めて、本作品は無難な選択といえると思う。
曲群としては2つめのト長調が、割と有名ではないか?
あとは、1枚目の11トラックの、チェロとの2重奏が、切々としていて訴えるものがある。私には、全曲中でもっとも印象に残る出色の名演に聴こえる。
バルヒェットの演奏において、たとえば解釈の斬新さとか、そういったものがあるのかどうかは、ちょっとわからないが、私はオーソドックスな演奏という印象を受ける。
なお、伴奏はチェンバロであり、全体としてボトムが軽くなる感じはあるものの、ヴァイオリン自体が中域から高域に特徴があるためか、それほど気にはならない。


![THE VENTURES - 45th Anniversary Live [1/9] The Ventures](http://img.youtube.com/vi/yjLFMCj82PI/3.jpg)



