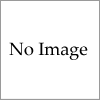The Dollar Crisis: Causes, Consquences, Cures / Revised and updated
レビュータイトルは、訳者の感想を引用した。金本位制をやめてから、アメリカは無制限に対外債務をふくらませている。アメリカは貿易赤字国になり、アメリカに輸出した貿易黒字国は、稼いだドルでアメリカの資産(国債や株など)を買う。ドルを自国通貨に交換すると、自国通貨高になってしまい輸出競争力が落ちてしまうからドルのままで投資する。このようなメカニズムによってドルはアメリカに還流し、アメリカの消費を支え、かつ、アメリカの対外債務はどんどん膨らむ。世界経済はアメリカの輸入、すなわち、借金ベースの消費に大きく依存している。しかし、アメリカの資産がもはや安全ではない、もはや買いたい資産がない、という臨界点に達したらこのメカニズムは崩壊し、ドルは大暴落を起こす・・・という話である。2003年の本であるが、2010年現在、ドルはまだ暴落していない。かといって、著者が指摘するリスクが去ったわけでもない。むしろ着々と悪化しているようにも見える。
著者の提案する処方箋「国際最低賃金制(その名の通り、国際的に最低賃金を決める制度)」は、人工的に世界の経済格差を是正するという意味でとてもおもしろいと思った。
あーなればこーなる、という論理は比較的明快な本だと思う。その一方、部分部分で断定的なところもあり、本当にそうなのか?と思う部分もあった。経済学の本は多かれ少なかれそういう部分があるが。
著者の提案する処方箋「国際最低賃金制(その名の通り、国際的に最低賃金を決める制度)」は、人工的に世界の経済格差を是正するという意味でとてもおもしろいと思った。
あーなればこーなる、という論理は比較的明快な本だと思う。その一方、部分部分で断定的なところもあり、本当にそうなのか?と思う部分もあった。経済学の本は多かれ少なかれそういう部分があるが。

パブロフの人
思いがけず始まった我が家の介護生活のスタートと重なり、引き込まれるように一気に読み通した。
作者の両親のようにまるで社会との繋がりを遮断している義父母のわがままを自分なりにたたみかけることができればと
考えていたが、本中の主人公の育ち方、生き方、裁判員裁判の様子を読むにつけそれまでの自分のことが少し客観的に思えてきて
むしろ本中の登場人物の方になりきっていた。
作者の両親のようにまるで社会との繋がりを遮断している義父母のわがままを自分なりにたたみかけることができればと
考えていたが、本中の主人公の育ち方、生き方、裁判員裁判の様子を読むにつけそれまでの自分のことが少し客観的に思えてきて
むしろ本中の登場人物の方になりきっていた。

ダンカンのかわったきてき (きかんしゃトーマスとなかまたち―トーマスのテレビ絵本)
ちょっぴりわがままなダンカンが、汽笛が鳴らなくなったために
パイプオルガンを汽笛代わりにつんで走るお話・・・。
汽笛を鳴らす場面で、汽笛の代わりにパイプオルガンがプワァー
と鳴ったのかと想像するとおかしくて、子供より私の方が楽しん
で読ませてもらいました。
パイプオルガンを汽笛代わりにつんで走るお話・・・。
汽笛を鳴らす場面で、汽笛の代わりにパイプオルガンがプワァー
と鳴ったのかと想像するとおかしくて、子供より私の方が楽しん
で読ませてもらいました。