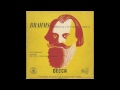田中角栄 - 戦後日本の悲しき自画像 (中公新書)
よくも悪くも戦後の日本を代表する政治家だった。今の小粒な政治家に比べると場数も踏んでいたのだなと改めて思った。
長年密着取材していた筆者だからこそ経験できた人間臭い取材も数多くあり面白かった。
長年密着取材していた筆者だからこそ経験できた人間臭い取材も数多くあり面白かった。

田原総一朗の遺言 永山則夫と三上寛/田中角栄 [DVD]
かつて平岡正明スピークスの「クロスオーバー音楽塾(講談社)」の中で、三上寛が登場し次のような発言をしていた。「田原さんの番組で小泊に行ったんだ。ところが小泊は三回の大火で焼かれたんで、家はみな新しい。田原さん狂っちまってね、流木があって、婆さんがガックリきていて、イタコの口寄せがあるという青森のイメージがないんだ。そこで、やらせをやるのよ。俺はバカらしくなって帰っちゃったら、あとで三上は逃げたと言われた(笑)。」・・・・この発言の元となったドキュメンタリーが1970年作品のこの本編であった。
最初に断っておくが、この作品は連続射殺魔・永山則夫を扱ったものではない。同じ郷里・青森から上京し、当時まったく無名であったフォークシンガー・三上寛に焦点が当てられている。1969年6月に三上は田原と最初に会っている。新聞配達の顧客であった人から天井桟敷を退団したカルメン・マキが「今度、新しい劇団を作るからオモシロイ奴を紹介してくれないか」との誘いで出掛けていったのが東京12チャンネルで、ロビーにいたのがディレクターの田原とマキ、りりィ、マキのヒモであった支那虎であった。田原は直感的にこの青森出身の若者(この時、三上は19歳であった)と番組を作ってみたいと思ったという。「もう一人の永山則夫・三上寛」はこうして始まった。収録作品は新聞配達をしていた三上寛へのインタビューから始まる。「永山は東京に負けたんだ。しかし俺は負けない。俺は俺自身の殺し方をするんだ。芸術家はみな殺す。特に詩人といった連中はみな殺す。」この時の三上は目が血走り、殺気立っている。三上自身は本当は詩人になりたくて上京して来たのであった。その詩人を殺すとは、どういうことなのだろうか。渋谷のライブハウス「ステーション70」で「カラス」を熱唱する三上。背後では「田舎から出て来て、土着とか第二の永山とか言われて、そんなに有名になりたいのかね・・・」といった罵詈雑言が流れ、意図的に三上を追い詰めていく。場は暗転して、三上は新宿のホコ天にいた。次から次へと若者をつかまえて「永山を知ってるだろう?津軽弁による芝居をやりたいんだ。そこで、あんたに"東京の人"の役をやって欲しいんだ。どうかね?ウンと津軽をバカにしてくれればそれでいいんだ」口角沫を飛ばす三上の誘いに誰もが拒絶する。田原と三上は青森の小泊に乗り込む。かつての中学の同級生に会い「永山の芝居をやりたいんだ。一緒に東京に行こう」と津軽弁でまくしたてる。そもそも、この永山の芝居というものが、どのようなモチーフで、どのような内容を含んでいるかは全く明らかにされていない。唯々、永山を引き合いに出して扇情的に議論を吹っ掛けているのである。かつての同級生を前にして三上は心情を吐露する・・・「みんな永山だと思うんだ。永山が一番偉いところは、人を殺してまでも生きていきたいと思ったところだよ。俺は生きたいんだよ。人を殺してまでも生きたいんだよ・・・」
そして40年ぶりに田原総一朗と三上寛はこのドキュメンタリーを振り返る。三上は、永山が捕まったとき「正直、津軽衆から全国に名を挙げた永山の犯罪を喜んだ」と回想する。東北という抑圧された土地から突破口のようなものを開けてくれたのが永山則夫だったという理解である。彼の中では永山は真逆のヒーローでありつづけた。そして、例の永山の芝居については、「当時は全共闘に象徴される怒れる若者の時代であった。しかし彼らは大学生である。中卒・高卒である我々にも表現する何かが欲しかった」と述懐する。1970年、団塊世代の大学進学率はわずか15%である。圧倒的にこの時代の高度経済成長を支えたのは"金の卵"といわれた中卒・高卒者であった。三上の父は小泊村の役所勤めであったため、三上は高校に進学できた一人であった。しかも警察学校に進んでいたのだから、優等生だったのである。その事が残りの同期生に対する負い目でもあった。小泊の同期生120名のうち高校に進めたのはわずか10名で、残りは漁師になるか東京に集団就職するかであった。そして、そのほとんどが職を転々とし、流浪するのである。故郷からは弾き飛ばされ、また東京からも弾き飛ばされるのである。
ここで田原から衝撃的な告白が述べられる。田原はカルメン・マキのドキュメントをすでに発表していた。つまり、マキに歌を歌わせたらどうかと天井桟敷主宰の寺山修司に話を持ちかけたのは田原自身であって、マキが歌った「時には母のない子のように」が大ヒットしたのである。カルメン・マキと三上寛。この個性的な二人と出会って、田原はこのドキュメンタリーを通して三上を第二のマキにしたかったと述べている。しかし、皮肉にも三上のレコードデビューに手を貸したのは田原の上司であった、ばばこういち氏であった。ステーション70で歌っていた三上をばばこういちは訪れて密かに注目していたのである。ところでこの渋谷のステーション70というライブハウスは新左翼や新右翼の活動家が出入りする政治的空間でもあった。オーナーである牧田吉明は三菱重工業の社長の御曹司であったが、裏ではピース缶爆弾事件に係わった「爆弾屋」の通称を持つアナーキストであった。阿部薫、吉沢元治、高柳昌行らのフリージャズメンたちが熱い演奏を繰り返していたのもこの場であった。三上はここで阿部勉という楯の会の若きリーダーとも知遇を得ている。極左極右の二人の理論家に見いだされたということは、その後の三上の歌を決定づけるものであった。彼の初期作品に「小便だらけの湖」というアナーキーな作品があるけれど、この頃の三上の心境を実にうまく表出していると思う。郷里・小泊と東京という磁場に引き裂かれた三上の怨情がこの歌にはある。三上は言う。「音楽家とか芸術家という者は毒をまき散らすものであり、犯罪的でなければ、その存在価値はない。己の暴力を管理する能力を持った者が真の芸術家である。」また、この頃深く心酔していた寺山修司から「革命的な歌を歌う必要などないんだよ。歌を革命すればいいんだよ。」と励まされたという。ここに三上寛の原点があるような気がしてならない。その後、40年間、三上には歌に対する確固たるスタンスを守ってきたという自負を読み取ることができる。最後に彼の代表曲である「夢は夜ひらく」を熱唱してこのDVDは終わる。ひとつだけ残念に思ったのは、この作品のできあがった経緯を三上寛本人の口から聞き出せなかったことである。40年前、ドキュメンタリー作家・田原総一朗とフォークシンガー・三上寛の熱い蜜月期があったのである。
最初に断っておくが、この作品は連続射殺魔・永山則夫を扱ったものではない。同じ郷里・青森から上京し、当時まったく無名であったフォークシンガー・三上寛に焦点が当てられている。1969年6月に三上は田原と最初に会っている。新聞配達の顧客であった人から天井桟敷を退団したカルメン・マキが「今度、新しい劇団を作るからオモシロイ奴を紹介してくれないか」との誘いで出掛けていったのが東京12チャンネルで、ロビーにいたのがディレクターの田原とマキ、りりィ、マキのヒモであった支那虎であった。田原は直感的にこの青森出身の若者(この時、三上は19歳であった)と番組を作ってみたいと思ったという。「もう一人の永山則夫・三上寛」はこうして始まった。収録作品は新聞配達をしていた三上寛へのインタビューから始まる。「永山は東京に負けたんだ。しかし俺は負けない。俺は俺自身の殺し方をするんだ。芸術家はみな殺す。特に詩人といった連中はみな殺す。」この時の三上は目が血走り、殺気立っている。三上自身は本当は詩人になりたくて上京して来たのであった。その詩人を殺すとは、どういうことなのだろうか。渋谷のライブハウス「ステーション70」で「カラス」を熱唱する三上。背後では「田舎から出て来て、土着とか第二の永山とか言われて、そんなに有名になりたいのかね・・・」といった罵詈雑言が流れ、意図的に三上を追い詰めていく。場は暗転して、三上は新宿のホコ天にいた。次から次へと若者をつかまえて「永山を知ってるだろう?津軽弁による芝居をやりたいんだ。そこで、あんたに"東京の人"の役をやって欲しいんだ。どうかね?ウンと津軽をバカにしてくれればそれでいいんだ」口角沫を飛ばす三上の誘いに誰もが拒絶する。田原と三上は青森の小泊に乗り込む。かつての中学の同級生に会い「永山の芝居をやりたいんだ。一緒に東京に行こう」と津軽弁でまくしたてる。そもそも、この永山の芝居というものが、どのようなモチーフで、どのような内容を含んでいるかは全く明らかにされていない。唯々、永山を引き合いに出して扇情的に議論を吹っ掛けているのである。かつての同級生を前にして三上は心情を吐露する・・・「みんな永山だと思うんだ。永山が一番偉いところは、人を殺してまでも生きていきたいと思ったところだよ。俺は生きたいんだよ。人を殺してまでも生きたいんだよ・・・」
そして40年ぶりに田原総一朗と三上寛はこのドキュメンタリーを振り返る。三上は、永山が捕まったとき「正直、津軽衆から全国に名を挙げた永山の犯罪を喜んだ」と回想する。東北という抑圧された土地から突破口のようなものを開けてくれたのが永山則夫だったという理解である。彼の中では永山は真逆のヒーローでありつづけた。そして、例の永山の芝居については、「当時は全共闘に象徴される怒れる若者の時代であった。しかし彼らは大学生である。中卒・高卒である我々にも表現する何かが欲しかった」と述懐する。1970年、団塊世代の大学進学率はわずか15%である。圧倒的にこの時代の高度経済成長を支えたのは"金の卵"といわれた中卒・高卒者であった。三上の父は小泊村の役所勤めであったため、三上は高校に進学できた一人であった。しかも警察学校に進んでいたのだから、優等生だったのである。その事が残りの同期生に対する負い目でもあった。小泊の同期生120名のうち高校に進めたのはわずか10名で、残りは漁師になるか東京に集団就職するかであった。そして、そのほとんどが職を転々とし、流浪するのである。故郷からは弾き飛ばされ、また東京からも弾き飛ばされるのである。
ここで田原から衝撃的な告白が述べられる。田原はカルメン・マキのドキュメントをすでに発表していた。つまり、マキに歌を歌わせたらどうかと天井桟敷主宰の寺山修司に話を持ちかけたのは田原自身であって、マキが歌った「時には母のない子のように」が大ヒットしたのである。カルメン・マキと三上寛。この個性的な二人と出会って、田原はこのドキュメンタリーを通して三上を第二のマキにしたかったと述べている。しかし、皮肉にも三上のレコードデビューに手を貸したのは田原の上司であった、ばばこういち氏であった。ステーション70で歌っていた三上をばばこういちは訪れて密かに注目していたのである。ところでこの渋谷のステーション70というライブハウスは新左翼や新右翼の活動家が出入りする政治的空間でもあった。オーナーである牧田吉明は三菱重工業の社長の御曹司であったが、裏ではピース缶爆弾事件に係わった「爆弾屋」の通称を持つアナーキストであった。阿部薫、吉沢元治、高柳昌行らのフリージャズメンたちが熱い演奏を繰り返していたのもこの場であった。三上はここで阿部勉という楯の会の若きリーダーとも知遇を得ている。極左極右の二人の理論家に見いだされたということは、その後の三上の歌を決定づけるものであった。彼の初期作品に「小便だらけの湖」というアナーキーな作品があるけれど、この頃の三上の心境を実にうまく表出していると思う。郷里・小泊と東京という磁場に引き裂かれた三上の怨情がこの歌にはある。三上は言う。「音楽家とか芸術家という者は毒をまき散らすものであり、犯罪的でなければ、その存在価値はない。己の暴力を管理する能力を持った者が真の芸術家である。」また、この頃深く心酔していた寺山修司から「革命的な歌を歌う必要などないんだよ。歌を革命すればいいんだよ。」と励まされたという。ここに三上寛の原点があるような気がしてならない。その後、40年間、三上には歌に対する確固たるスタンスを守ってきたという自負を読み取ることができる。最後に彼の代表曲である「夢は夜ひらく」を熱唱してこのDVDは終わる。ひとつだけ残念に思ったのは、この作品のできあがった経緯を三上寛本人の口から聞き出せなかったことである。40年前、ドキュメンタリー作家・田原総一朗とフォークシンガー・三上寛の熱い蜜月期があったのである。

田中角栄という生き方 (別冊宝島 2183)
元から気になっていた人物だったので、900円は安すぎと思った。読んでいると人生力学が濃い、「人から悪口を言われても気にするな、人の悪口は便所で済ませ」「学歴とは教養のある人を言う」「人を裏切るな」「名前くらいきちんと覚えろ」これは政治家ではなく、一人の日本人としてのたしなみをしつけてくれているような気がする。金権政治のボスと悪く書かれるが人間としては素晴らしい人だったと思った。こんな政治家あとにも先にも出ない気がする。