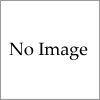
CHIBBY
オープニングを飾る2曲(1)(2)はそれぞれ伊秩弘将と林田健司作の極上ダンスポップス。
続いて壮大なミディアム(3)にアップテンポで軽快な(4)、
とどめに松尾清憲の必殺バラード(5)でもう腰砕け(個人的にナイスな取り合わせ!)。
爽やかなアレンジが真夏の海辺に合う井上ヨシマサの(7)。そして代表曲の(6)(8)に、
原田真二「さよならのわけもきかないで~Don't Cry Baby~」の歌詞違い(9)。
「東芝のお店」CM曲(10)はもしかしたら一般層にもっとも浸透した曲かも。
ジュリー・藤井フミヤ・久保田利伸などを彷彿とさせる伸びやかなヴォーカルは、
ただもうひたすらに甘美でエロい。
さらにジャニーズアイドル張りに端整な容貌の持ち主とくれぱ、もうあなた。
同郷のシャ乱Qを蹴散らし、同期のミスチルを突き放し、スター街道いざ驀進!
……となるはずでした、予定では。それなのに、ああそれなのに(以下省略)
続いて壮大なミディアム(3)にアップテンポで軽快な(4)、
とどめに松尾清憲の必殺バラード(5)でもう腰砕け(個人的にナイスな取り合わせ!)。
爽やかなアレンジが真夏の海辺に合う井上ヨシマサの(7)。そして代表曲の(6)(8)に、
原田真二「さよならのわけもきかないで~Don't Cry Baby~」の歌詞違い(9)。
「東芝のお店」CM曲(10)はもしかしたら一般層にもっとも浸透した曲かも。
ジュリー・藤井フミヤ・久保田利伸などを彷彿とさせる伸びやかなヴォーカルは、
ただもうひたすらに甘美でエロい。
さらにジャニーズアイドル張りに端整な容貌の持ち主とくれぱ、もうあなた。
同郷のシャ乱Qを蹴散らし、同期のミスチルを突き放し、スター街道いざ驀進!
……となるはずでした、予定では。それなのに、ああそれなのに(以下省略)

プロ直伝! 職業作曲家への道 ~ 曲作りを仕事にするための常識と戦術、そして心得
おそらく、世間一般では知られていないと思うんですが、世の中には2種類の「作曲家」がいます。
本書で取り上げられている「職業作曲家」と「芸術家タイプの作曲家」です。
(当然のことですが、実際にはグレー・ゾーンがあります)
「職業作曲家」は、音楽理論などのテクニックやノウハウを駆使して曲を作り込みます。
それに対し後者は、曲のイメージやサウンドが突然アタマにひらめくタイプです。
インスピレーションに従うだけであって、「さあ、曲を作ろう」と思って作曲する・できるワケではないのです。
「芸術家タイプの作曲家」は、それまでにない自由なメロディ・ラインやサウンドを提示するのに対し、「職業作曲家」の作る楽曲は、どうしても既存の音楽の延長線上にある曲がほとんどになります。
音楽というものは、本来、リスナーの感性や感情に訴えかけるような精神的「芸術作品」(オーバーですが)であって「商品」ではありません。
残念ながら日本では、この本に書かれているように、ベルトコンベアー方式で「音楽」という名の「商品」が量産されています。
日本の音楽業界では、効率的に納期を守って、ボツにしても気にせず次から次にコンペに新曲を提出してくれる「職業作家」が断然、重宝されるんです。
ある意味「ブラック企業」に通じるところがあります(笑)
しかし、音楽を作る側の姿勢として、本当に「数打ちゃ当たる」みたいなスタンスでいいのでしょうか?
洋楽に詳しい方なら分かると思いますが、海外のアーティストたちは「自分だけにしか作れない音楽」を作ること、目指すことが大前提であり、ゆえに苦悩しています。
そこに日本の音楽シーンとの、かなりの温度差を感じます。
わかりやすく絵画の世界に例えて言うと、ピカソのスタイルを真似て自分の描いた絵を売り出そうとしたら、いったいどのようなことになるのか?評価は?ということです。
世界中で音楽が、あらゆるジャンルを巻き込んで進化し続けているのに対し、日本では、どこか既視感のある楽曲や、過去のビッグ・ヒット、あるいは海外で流行しているサウンドをなぞっただけのモノが氾濫しているのは、こういった構造的な問題が大きいと思います。
いわゆる邦楽の「ガラパゴス・ポップ化」問題です。
ちょっと長くなりましたが、この2種類の作曲家の区別について著者の方は軽く触れるか触れないか程度でした。
そして、このような論調だと「芸術家タイプの作曲家」たちは、みなさんモチベーションを削がれてしまうのではないでしょうか?
以上の点を除いて、最後まで興味深く読み進めることができましたので、マイナス1で。
本書で取り上げられている「職業作曲家」と「芸術家タイプの作曲家」です。
(当然のことですが、実際にはグレー・ゾーンがあります)
「職業作曲家」は、音楽理論などのテクニックやノウハウを駆使して曲を作り込みます。
それに対し後者は、曲のイメージやサウンドが突然アタマにひらめくタイプです。
インスピレーションに従うだけであって、「さあ、曲を作ろう」と思って作曲する・できるワケではないのです。
「芸術家タイプの作曲家」は、それまでにない自由なメロディ・ラインやサウンドを提示するのに対し、「職業作曲家」の作る楽曲は、どうしても既存の音楽の延長線上にある曲がほとんどになります。
音楽というものは、本来、リスナーの感性や感情に訴えかけるような精神的「芸術作品」(オーバーですが)であって「商品」ではありません。
残念ながら日本では、この本に書かれているように、ベルトコンベアー方式で「音楽」という名の「商品」が量産されています。
日本の音楽業界では、効率的に納期を守って、ボツにしても気にせず次から次にコンペに新曲を提出してくれる「職業作家」が断然、重宝されるんです。
ある意味「ブラック企業」に通じるところがあります(笑)
しかし、音楽を作る側の姿勢として、本当に「数打ちゃ当たる」みたいなスタンスでいいのでしょうか?
洋楽に詳しい方なら分かると思いますが、海外のアーティストたちは「自分だけにしか作れない音楽」を作ること、目指すことが大前提であり、ゆえに苦悩しています。
そこに日本の音楽シーンとの、かなりの温度差を感じます。
わかりやすく絵画の世界に例えて言うと、ピカソのスタイルを真似て自分の描いた絵を売り出そうとしたら、いったいどのようなことになるのか?評価は?ということです。
世界中で音楽が、あらゆるジャンルを巻き込んで進化し続けているのに対し、日本では、どこか既視感のある楽曲や、過去のビッグ・ヒット、あるいは海外で流行しているサウンドをなぞっただけのモノが氾濫しているのは、こういった構造的な問題が大きいと思います。
いわゆる邦楽の「ガラパゴス・ポップ化」問題です。
ちょっと長くなりましたが、この2種類の作曲家の区別について著者の方は軽く触れるか触れないか程度でした。
そして、このような論調だと「芸術家タイプの作曲家」たちは、みなさんモチベーションを削がれてしまうのではないでしょうか?
以上の点を除いて、最後まで興味深く読み進めることができましたので、マイナス1で。








