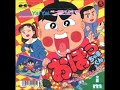誰でもが簡単にプレゼンテーションを成功させるための論理と心理のコツのコツ [DVD]
話はわかるけど、共感できないなぁ とか、気持ちはわかるけど、なんかヘンな理屈な気がする、なんて話を聞かされることがある。あるいは理屈ではそうだけど、実際には...なんてこともある。
別の例でいえば、煙草がやめられないのもそうかもしれない。論理的思考ではいいことは一つもないことはわかっているのに、心中は違っているから。
と、いうことは、論理と心理の両面から行くということを認識してかかれば【最強】ということ??
そしてプレゼンテーション に関してもまさにそれは当てはまる気がする。プレゼンに関する本などはいくつか買ったことがあるが、この心理と論理の両面から攻略するということを正面から教えるものはなかった気がする。
理屈で納得させるだけではなく、気持ちもそうさせる、ということができればプレゼンは大成功だと思う。と偉そうに書いている私は、たしかにこのDVDの講師の術中にはめられた...??
別の例でいえば、煙草がやめられないのもそうかもしれない。論理的思考ではいいことは一つもないことはわかっているのに、心中は違っているから。
と、いうことは、論理と心理の両面から行くということを認識してかかれば【最強】ということ??
そしてプレゼンテーション に関してもまさにそれは当てはまる気がする。プレゼンに関する本などはいくつか買ったことがあるが、この心理と論理の両面から攻略するということを正面から教えるものはなかった気がする。
理屈で納得させるだけではなく、気持ちもそうさせる、ということができればプレゼンは大成功だと思う。と偉そうに書いている私は、たしかにこのDVDの講師の術中にはめられた...??

必ず役立つ! 「○○(マルマル)の法則」事典 (PHP文庫)
白洲次郎が「西洋人とつき合うには、すべての言動にプリンシプルがはっきりしていることは絶対に必要である」と言っていますが、その通りで、西洋人はプリンシプル、つまり、法則が大好きなようです。国家にも企業も、社長にも課長にも、自然現象から企業の人事政策に至るまで、「どこかに法則性がないか」と探し回るのが西洋人の本性。逆に対象や相手に法則性が見出せないと、今度は不安になってしまうような気がします。
西洋人の法則好きな本性を万遍なく表しているのが本書。「こんなことまで法則にしなくても!」と思わせるくらいに楽しい本です。深読みすれば、そんな相手に、私たち日本人が、毎回、対症療法、ノー・プリンシプルで立ち向かうのは難しいのかと考えさせてもくれます。
西洋人の法則好きな本性を万遍なく表しているのが本書。「こんなことまで法則にしなくても!」と思わせるくらいに楽しい本です。深読みすれば、そんな相手に、私たち日本人が、毎回、対症療法、ノー・プリンシプルで立ち向かうのは難しいのかと考えさせてもくれます。

非言語(ノンバーバル)コミュニケーション (新潮選書)
言葉を伝えるためのコミュニケーションツールが発展し、今やインターネットによって気軽に時間と距離を超えたコミュニケーションが可能となった。
しかし、言葉だけ、特に文字だけのコミュニケーションを円滑を可能とする条件は意外にも厳しく、よく知った間柄でさえちょっとしたことが大きな誤解を招いたといった経験は多くの人が持っていることだと思う。
本書に示された非言語メディア種類や特徴を知ることで、相手の本当の気持ちを知るきっかけになるとは思うがこれだけが全てではない。
文化や地域といった固有の「状況(コンテクスト)」を理解せずに本当のコミュニケーションはできないということが本質であり、これは非言語のみならず言語でのコミュニケーションを前提にしても当然当てはまる。
突き詰めるとコミュニケーションは、如何に相手を理解しようとするか。
これに尽きるのではないかと、考えさせられてしまう。
しかし、言葉だけ、特に文字だけのコミュニケーションを円滑を可能とする条件は意外にも厳しく、よく知った間柄でさえちょっとしたことが大きな誤解を招いたといった経験は多くの人が持っていることだと思う。
本書に示された非言語メディア種類や特徴を知ることで、相手の本当の気持ちを知るきっかけになるとは思うがこれだけが全てではない。
文化や地域といった固有の「状況(コンテクスト)」を理解せずに本当のコミュニケーションはできないということが本質であり、これは非言語のみならず言語でのコミュニケーションを前提にしても当然当てはまる。
突き詰めるとコミュニケーションは、如何に相手を理解しようとするか。
これに尽きるのではないかと、考えさせられてしまう。