
蛎崎波響の生涯
中村さんの名著の一つだろう。蠣崎波響という人は松前藩の家老で、画と漢詩に長けていたが、メインは政治であり、松前藩の復活の為に力を尽くした。しかし、その後の明治維新を考えると、彼の今日に於ける価値は画と漢詩にあるといえよう。この本は図版も綺麗で、とても好い本であり、江湖にお薦めしたい。

王朝物語 (新潮文庫)
本書で取り上げられる王朝物語(平安時代後期から室町時代前期にかけて作られた小説・物語群)に関しての知識・理解については、中村真一郎氏に及ぶ作家はいないだろう。ただ、本書はそういった作品の単なる解説や読みではなく、中村氏側に王朝物語をひきつけ、現代的な視点から新たに王朝物語の中に含まれる“文学的な富”を見出そうという試みである。大学でフランス文学を学び、フランスだけでなくドイツ・イギリス文学にも通じ、古典的な作品にも造詣がある著者ならではの、独特な見解が多数含まれており、あまりにも広々とした文学世界に関する記述についていくことが、大変であることは言うまでもない。
個々に取り上げられた文学作品について、あまり拘泥してしまうと、読み進めることは難しい。むしろ、とにかく通読して、気になった部分に書かれた文学作品に接し、中村氏の見解と改めて向き合うべきなのだろう。
なお、王朝物語群については笠間書院より『中世王朝物語全集』が刊行されているので、古典文学全集からもれた作品なども入手できる。
個々に取り上げられた文学作品について、あまり拘泥してしまうと、読み進めることは難しい。むしろ、とにかく通読して、気になった部分に書かれた文学作品に接し、中村氏の見解と改めて向き合うべきなのだろう。
なお、王朝物語群については笠間書院より『中世王朝物語全集』が刊行されているので、古典文学全集からもれた作品なども入手できる。

文章読本 (新潮文庫)
これは、著者自身が若いころ受け取った手紙で、長年これが実は恋文だったことに気づかなかったという体験談が10ページ目から11ページ目にかけて書いてある。表面的な意味はわかっても、その奥の真意はつかめないことがある。そこから、文章論がスタートする。解説は、きわめて平明。
さまざまな文体。いきなり、ユリシーズ(ジョイス)の大胆な和訳が登場するかと思えば、山路愛山、ツルゲーネフの明治時代の和訳、二葉亭の浮雲、円朝の落語、花袋の布団、鏡花の歌行灯、..... 少し省略して、三島の宴のあと、などなど。
こうして見るうちに、文語と江戸の話し言葉の乖離、言文一致運動、口語文の市民権獲得、翻訳文、文体実験の歴史が自然に了解される。文章読本の形をとった近代文学史としても異存はない。
欲を言えば、宮沢賢治をとりあげなかったこと。著者は音痴であり、音韻的文体論は手に余ったのであろう。草野心平はどうなのか。やや不満が残る。ましてや、筒井康隆の「バブリング創世記」は、理解の外であろう。
さまざまな文体。いきなり、ユリシーズ(ジョイス)の大胆な和訳が登場するかと思えば、山路愛山、ツルゲーネフの明治時代の和訳、二葉亭の浮雲、円朝の落語、花袋の布団、鏡花の歌行灯、..... 少し省略して、三島の宴のあと、などなど。
こうして見るうちに、文語と江戸の話し言葉の乖離、言文一致運動、口語文の市民権獲得、翻訳文、文体実験の歴史が自然に了解される。文章読本の形をとった近代文学史としても異存はない。
欲を言えば、宮沢賢治をとりあげなかったこと。著者は音痴であり、音韻的文体論は手に余ったのであろう。草野心平はどうなのか。やや不満が残る。ましてや、筒井康隆の「バブリング創世記」は、理解の外であろう。
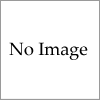
秋刀魚の味 [DVD]
小津監督の最後の作品。監督自身は最後の作品のつもりではなかったと思うのだが、数多くの名作を残した監督の最後の作品…一抹の感傷を持ってみてしまう。
そのせいか、戦後小津映画の最もベーシックなテーマである「独身の父と娘の結婚」というテーマが語られ、それも「晩春」や「麦秋」を思わせるようなストレート形で描かれていると思う。ユーモアの感覚も見られるが、「秋日和」や「彼岸花」に比べると、ユーモアよりも「父と娘」のテーマに比重がかかっていると感じる。
ただ、この作品独自の観点もあって、かつての恩師の姿…婚期を逃したままの娘と父の姿がけっこう厳しく描かれる。このあたりは、人間、何事も潮時があって、結婚しなくちゃ…というのが小津監督の考えかも知れないし、一方、ラストのあたりでは「人間は所詮は孤独なもの」という考えも伝わってくる。人間には定めがあり、そのためには孤独でも耐えていかなければならない、ということなのだろうか?
岩下志麻の婚礼の姿、美しくて、日本の映画史の中でも屈指の花嫁姿だったと思う。
そのせいか、戦後小津映画の最もベーシックなテーマである「独身の父と娘の結婚」というテーマが語られ、それも「晩春」や「麦秋」を思わせるようなストレート形で描かれていると思う。ユーモアの感覚も見られるが、「秋日和」や「彼岸花」に比べると、ユーモアよりも「父と娘」のテーマに比重がかかっていると感じる。
ただ、この作品独自の観点もあって、かつての恩師の姿…婚期を逃したままの娘と父の姿がけっこう厳しく描かれる。このあたりは、人間、何事も潮時があって、結婚しなくちゃ…というのが小津監督の考えかも知れないし、一方、ラストのあたりでは「人間は所詮は孤独なもの」という考えも伝わってくる。人間には定めがあり、そのためには孤独でも耐えていかなければならない、ということなのだろうか?
岩下志麻の婚礼の姿、美しくて、日本の映画史の中でも屈指の花嫁姿だったと思う。






