
スヴャトスラフ・リヒテル・コンサート/モスクワ音楽院ライヴ1976 [DVD]
曲目が表示されて無いので以下に示します。
・ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第1番へ短調 op.2-1
・シューマン:ウィーンの謝肉祭の道化 op.26
・ベートーヴェン:バガテル ト長調 op.126-1
・ドビュッシー:前奏曲集第1巻〜第3曲『野を渡る風』
・ドビュッシー:前奏曲集第2巻〜第8曲『水の精』
・ラフマニノフ:前奏曲 嬰ト短調 op.32-12
・ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第1番へ短調 op.2-1
・シューマン:ウィーンの謝肉祭の道化 op.26
・ベートーヴェン:バガテル ト長調 op.126-1
・ドビュッシー:前奏曲集第1巻〜第3曲『野を渡る風』
・ドビュッシー:前奏曲集第2巻〜第8曲『水の精』
・ラフマニノフ:前奏曲 嬰ト短調 op.32-12
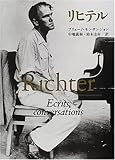
リヒテル
リヒテルの音を聴くたび「抑制されたダイナミズム」という言葉が浮かぶ。おのれの中で激しく渦巻くものを、冷静に見つめている姿がある。で、リヒテルとはだれだったのか?ドイツ人の父をスターリンの粛清で失った悲劇の人?亡命を恐れた当局に長らく西側公演を禁じられた「幻の巨匠」?前半は本人のインタビューを一人称でまとめた回顧録。時代のきしみの中で、リヒテルがどう音を紡いでいったかを知る手がかりがある。そして後半は、リヒテルが長年綴った「音楽備忘録」。自己の演奏への過酷なまでに突き放した分析や同時代への演奏家への辛辣な評が、しごく端的に記されている。マエストロと呼ばれた男の肉声は、その語り口がたんたんとしているだけに、悠々とした響きがする。

リヒテルと私 河島みどり 著
マエストロが生きていれば、きっと、この本は出版できなかったでしょう。だれでも、プライベートをあれこれ書かれるのは、いやなもの。巨匠、リヒテルの素顔をのぞける、最初で最後のチャンスでしょうね。

カーネギー・ホール・リサイタル1960
即興性あふれるリヒテルの演奏!特にショパンのツケルツォNo4とプロコフィエフ自身のお墨付き、ソナタNO6&束の間の幻影は、特筆物です。すべてのフレーズが生命力あふれる表現で、曲の本質を見事に描き出しています。

リヒテルは語る―人とピアノ、芸術と夢
リヒテルという名前は、特別な響き、輝きを持っている。
その演奏は、聴き手を音楽の神殿に連れていく。そこに何の説明もいらない。
独学でピアノ演奏を習得した後、名伯楽ネイガウスの教え子となる。
長らく鉄のカーテンの東側で知られざる存在だったが、ベートーヴェンのテンペストでアルバムデビューし、
カーネギーホールなどのアメリカ公演は、絶賛で迎えられる。
大ホールでのコンサートよりも、旅を重ねる中での小ホールコンサートを愛し、
膨大なレパートリーを持ちながら、まとまった全集録音はほとんど行わなかった。
そのリヒテルが語る。何を? どんなふうに? この本を読むまで、
語るリヒテルというのは想像ができなかった。しかしここでリヒテルは、文字通り語っている。
著者の横で、ピアノの前で、散歩しながら、語り続ける。音楽史を飾る作曲家たちやクラシック音楽については
もちろんのこと、プルースト、ドストエフスキー、トーマス・マン、ゴーゴリー、シェイクスピア、
ヴァン・ゴッホ、ルノアール、パゾリーニ、ジャン・コクトー、クロサワ、演劇、建築、夢、空想。
ほとんど間断なく次から次に、彼の連想の中で様々な事柄がつながっていく。
散歩の途中、突然立ち止まり、空を見上げ、「青。第4番嬰ヘ長調ソナタは、青」と、
スクリャービン・ソナタについてつぶやく。
彼の中ではそんなに豊富な情報が渦巻きながら、あのピアノ演奏になっていたとは。
ただ、それらは読んでいて刺激的で楽しいが、あの演奏そのものとは一線を画している。
あくまでも演奏は演奏で、それ自体の輝きの中にある。
「ベートーヴェンの第32番ソナタは、舞台に出て椅子に座るやいなや即座に引き始めなくてはダメだ。
気が狂ったかのようにね。(第4章 人間とピアノ)」
巻末に詳細な「リヒテル・レパートリー・リスト」がある。訳は、グールド関連で有名な宮澤氏。
装丁は造本の名手・菊地信義氏によって仕上げられている。
その演奏は、聴き手を音楽の神殿に連れていく。そこに何の説明もいらない。
独学でピアノ演奏を習得した後、名伯楽ネイガウスの教え子となる。
長らく鉄のカーテンの東側で知られざる存在だったが、ベートーヴェンのテンペストでアルバムデビューし、
カーネギーホールなどのアメリカ公演は、絶賛で迎えられる。
大ホールでのコンサートよりも、旅を重ねる中での小ホールコンサートを愛し、
膨大なレパートリーを持ちながら、まとまった全集録音はほとんど行わなかった。
そのリヒテルが語る。何を? どんなふうに? この本を読むまで、
語るリヒテルというのは想像ができなかった。しかしここでリヒテルは、文字通り語っている。
著者の横で、ピアノの前で、散歩しながら、語り続ける。音楽史を飾る作曲家たちやクラシック音楽については
もちろんのこと、プルースト、ドストエフスキー、トーマス・マン、ゴーゴリー、シェイクスピア、
ヴァン・ゴッホ、ルノアール、パゾリーニ、ジャン・コクトー、クロサワ、演劇、建築、夢、空想。
ほとんど間断なく次から次に、彼の連想の中で様々な事柄がつながっていく。
散歩の途中、突然立ち止まり、空を見上げ、「青。第4番嬰ヘ長調ソナタは、青」と、
スクリャービン・ソナタについてつぶやく。
彼の中ではそんなに豊富な情報が渦巻きながら、あのピアノ演奏になっていたとは。
ただ、それらは読んでいて刺激的で楽しいが、あの演奏そのものとは一線を画している。
あくまでも演奏は演奏で、それ自体の輝きの中にある。
「ベートーヴェンの第32番ソナタは、舞台に出て椅子に座るやいなや即座に引き始めなくてはダメだ。
気が狂ったかのようにね。(第4章 人間とピアノ)」
巻末に詳細な「リヒテル・レパートリー・リスト」がある。訳は、グールド関連で有名な宮澤氏。
装丁は造本の名手・菊地信義氏によって仕上げられている。







