
蝉しぐれ (文春文庫)
初めて藤沢作品に触れた.この作品,主人公の文四郎の青春を等身大で描いた小説で,父の死,母への気持ち,恋,親友との友情,剣,といったいくつもの場面を,文四郎が感受性豊に行動的に生きていく様が描かれている.そして幼馴染の初恋の人を救い,後年再会し,想いを確かめ合う.電車の中で,涙ぐみそうだった.自分に対して素直な主人公の生き方に共感できる.文章も,なんとも言えない描写の妙があり,読むことを楽しく嬉しくさせてくれる.この歳(30台後半)だからこその感動かもしれないが,良い作品に出会えた感が強い.

新装版 雪明かり (講談社文庫)
四十を超えて初めて読んだ時代劇小説です。
暇つぶしに手に取った文庫でした。
しぶい。とてつもなく、しぶい。
チャンドラーやエルロイや北方(現代もの)とも違う、人間の襞の描き方。
心に染み入る文章とはこのような文章なのでしょう。
日本のハードボイルドとは、時代劇にあったのですね。
「穴熊」は、まさに絶品でした。
潔癖、完全は、時に、絶望的な自己満足になってしまうということが、
悲しくもあり、高貴にも感じました。
藤沢周平を読まなかったことを悔やみ、読んだ偶然に感謝します。
暇つぶしに手に取った文庫でした。
しぶい。とてつもなく、しぶい。
チャンドラーやエルロイや北方(現代もの)とも違う、人間の襞の描き方。
心に染み入る文章とはこのような文章なのでしょう。
日本のハードボイルドとは、時代劇にあったのですね。
「穴熊」は、まさに絶品でした。
潔癖、完全は、時に、絶望的な自己満足になってしまうということが、
悲しくもあり、高貴にも感じました。
藤沢周平を読まなかったことを悔やみ、読んだ偶然に感謝します。

蝉しぐれ (文春文庫)
鮮やかな緑色の樹木と透明な夏の空気。
場面は秋であっても冬であっても、全編を通してこのようなイメージで満たされている小説である。
藤沢作品はもちろん、時代小説というものを初めて読んだのだが、この小説で初めて
「話の筋によって心が躍らされる」という体験をした。それぞれの章に独特のリズムがあり、
ぐいぐいと惹きこまれている自分に、ふと気がつくのがおもしろい。
「蝉しぐれ」は読んでいるとき、あるいは読み終わった後になってようやく思いがいたって、
じんわりしたりジーンとしたり、すがすがしい涙を流したりするように書かれている。
いつまでも変わらない人間の心、気持ち、思いが、ほどよくちりばめられているのは、
現代小説ではなく、読み手それぞれが好きなように思いをはせることのできる時代小説ならではだと思う。
のんびりと時間のとれるときに、じっくりと読んで欲しい。
場面は秋であっても冬であっても、全編を通してこのようなイメージで満たされている小説である。
藤沢作品はもちろん、時代小説というものを初めて読んだのだが、この小説で初めて
「話の筋によって心が躍らされる」という体験をした。それぞれの章に独特のリズムがあり、
ぐいぐいと惹きこまれている自分に、ふと気がつくのがおもしろい。
「蝉しぐれ」は読んでいるとき、あるいは読み終わった後になってようやく思いがいたって、
じんわりしたりジーンとしたり、すがすがしい涙を流したりするように書かれている。
いつまでも変わらない人間の心、気持ち、思いが、ほどよくちりばめられているのは、
現代小説ではなく、読み手それぞれが好きなように思いをはせることのできる時代小説ならではだと思う。
のんびりと時間のとれるときに、じっくりと読んで欲しい。

隠し剣 鬼の爪 通常版 [DVD]
感嘆させられるのはこだわりのロケである。日本にはまだこれだけ美しい風景があったのか。月山のロングショット、これだけでも「観て良かった」と思わずにいられない。主役の片桐宗蔵を演じる永瀬氏もこの風景に溶け込んでいる。本当にこういう侍がいたのではないか、と思わせる。それもそのはずで、永瀬氏は本当に月代を剃って撮影に望んだそうである。
「弁慶めし」や「どんがら汁」などの味覚も登場し、それがまた美味しそうである。また下級武士の質素な暮らしぶりもよく表現されていると思う。
武士は自由に結婚が出来なかった。奉公人の「きえ」を愛しく思っているのだが、現代のように率直に表現できない。宗蔵は大胆な行動に出るのだが、これも作品ならではの試みと言えよう。
「海坂藩」という架空の藩ではあるが、時代は幕末に設定されている。ということで、戊辰戦争では最後まで戦った藩。洋式調練の様子が出てくるが、当時この藩が実際に使った図柄の旗が登場する。そんな発見も楽しみのひとつだ。
「鬼の爪」という秘剣で人を殺めることになるのだが、これが意外なところに使われる。まさしく秘剣なので見逃さないよう留意されたい。
「弁慶めし」や「どんがら汁」などの味覚も登場し、それがまた美味しそうである。また下級武士の質素な暮らしぶりもよく表現されていると思う。
武士は自由に結婚が出来なかった。奉公人の「きえ」を愛しく思っているのだが、現代のように率直に表現できない。宗蔵は大胆な行動に出るのだが、これも作品ならではの試みと言えよう。
「海坂藩」という架空の藩ではあるが、時代は幕末に設定されている。ということで、戊辰戦争では最後まで戦った藩。洋式調練の様子が出てくるが、当時この藩が実際に使った図柄の旗が登場する。そんな発見も楽しみのひとつだ。
「鬼の爪」という秘剣で人を殺めることになるのだが、これが意外なところに使われる。まさしく秘剣なので見逃さないよう留意されたい。
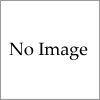
たそがれ清兵衛 [VHS]
「たそれが清兵衛」は、山田洋次監督にとって「運が良けりゃ」(1966)以来久しぶりの時代劇だという。それまで現代劇を撮り続けてきた山田監督、この映画はそれまでの時代劇のイメージとはかなり異なる。
庄内弁を喋る登場人物(他監督の藤沢周平の映像化は標準語を喋る)、無精ひげにきれいに剃られていない月代(さかやき)。どこか薄汚れて見えるが、当時の下級武士はきっとこんな生活ぶりだったのだろう…と思わせる。
そのリアル(に感じる)侍の生活ぶりからは、典型的な時代劇とは異なったストーリーが生まれる。敵討とかそんな話ではなく、封建時代の中での人々のリアルな生活ぶり。山田監督の狙いはここにあったのかも? とも思う。他の山田映画と同じく、故郷、家族、人と人との絆、社会の周辺にいる人たちを愛着をもって描く…それがそのまま江戸時代に移されているのだと思う。見方を変えれば、時代劇であってもやっぱり山田映画、なのだと思う。
真田広之はそんな物語の主人公をこれまたリアルに演じている。時代劇の中の人物でありながら、なぜか身近に感じてしまうような侍像になっている。そして宮沢りえの朋江は、穏やかな雰囲気で、映画の流れによくあったキャラクターだと思った。
ラストシーン、時代の流れの中で必死に生きていった主人公のことが語られる。「男はつらいよ」の中で寅さんが言っていたと思うが、普通の生活を黙々と地道に生きることが尊い…そんなことを思わせるラストだった。
庄内弁を喋る登場人物(他監督の藤沢周平の映像化は標準語を喋る)、無精ひげにきれいに剃られていない月代(さかやき)。どこか薄汚れて見えるが、当時の下級武士はきっとこんな生活ぶりだったのだろう…と思わせる。
そのリアル(に感じる)侍の生活ぶりからは、典型的な時代劇とは異なったストーリーが生まれる。敵討とかそんな話ではなく、封建時代の中での人々のリアルな生活ぶり。山田監督の狙いはここにあったのかも? とも思う。他の山田映画と同じく、故郷、家族、人と人との絆、社会の周辺にいる人たちを愛着をもって描く…それがそのまま江戸時代に移されているのだと思う。見方を変えれば、時代劇であってもやっぱり山田映画、なのだと思う。
真田広之はそんな物語の主人公をこれまたリアルに演じている。時代劇の中の人物でありながら、なぜか身近に感じてしまうような侍像になっている。そして宮沢りえの朋江は、穏やかな雰囲気で、映画の流れによくあったキャラクターだと思った。
ラストシーン、時代の流れの中で必死に生きていった主人公のことが語られる。「男はつらいよ」の中で寅さんが言っていたと思うが、普通の生活を黙々と地道に生きることが尊い…そんなことを思わせるラストだった。




![Black/Matrix II [ブラックマトリクスII] Game Sample - Playstation 2 ブラックマトリクス](http://img.youtube.com/vi/Mg-kgsQLh64/2.jpg)


