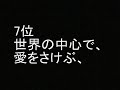Charlie Parker Omnibook: For C Instruments. (Treble Clef Version)
パーカーの有名テイクを採譜した定番本。
パーカー好きはもちろん、バップ好き、ジャズの勉強としてのバップへの取り組みなど、幅広い使い道があります。
C用のみではなく、Bb用、Eb用があります。
ただ、調がすべてハ調で扱いで臨時記号として表記されているのが、かなり見ずらかったりします。
パーカー好きはもちろん、バップ好き、ジャズの勉強としてのバップへの取り組みなど、幅広い使い道があります。
C用のみではなく、Bb用、Eb用があります。
ただ、調がすべてハ調で扱いで臨時記号として表記されているのが、かなり見ずらかったりします。

チャーリー・パーカー―モダン・ジャズを創った男
本書は、第1部:The Life of Charlie Parker、第2部:The Music of Charlie Parker の二部構成になっている。要は、伝記的な部分と、奏法分析の部分の2パートである。
パーカーの伝記やインタビュー本は、ライズナーの「チャーリー・パーカーの伝説」やラッセルの「バードは生きている」などの古典があるが、その後も関係者やミュージシャンから様々な発言が繰り返され、旧説と矛盾する説も多々あって収拾のつかない状況だったと思う。
本書の第1部では、こうした雑多な資料を適切に取捨選択し、新しい証拠も踏まえて、短いながらパーカーの人生の納得のいく素描になっていると思う。
第2部では、採譜された楽譜も多用して、年代順にパーカーのアドリブ技法の特徴を分析している。
特に、パーカーがビ・バップの根幹となる奏法を編み出し完成させていく1940年~43年は、レコーディング・ストなどの影響で音源がほぼ皆無だったが、近年発見された私家版録音などを基に、レスター・ヤング、コールマン・ホーキンス、バスター・スミス等からの影響関係を具に分析するあたりは、パーカー・ファン必読であろう。
この手の研究書としては、Thomas Owens や Henry Martin の著書(いずれも未訳)が有名だが、最近では濱瀬元彦氏の「チャーリー・パーカーの技法」という快著がある。が、これらはいずれも、楽理やコード理論をかなりのレヴェルでマスターしたミュージシャンやマニアでなければ読みこなすのは困難だろう。
このウォイデック氏の本は、楽譜を用い、コード関係の用語も頻出するが、逐次平易な言葉で要点を総括してくれているので、まったくコード理論を知らない人でもある程度ついていけるはずだ。(コードのイロハぐらいを多少知っている人なら充分読める。)
音楽を個人で楽しむのに理論や分析など関係ないという人も多いだろうが、ビ・バップ(=モダンジャズ)の最大の特徴は、アドリブの基礎として「コード進行」の概念を明確に打ち出し、そのコード進行に基づいてどこまでヴィヴィッドにかつ自由にアドリブできるか、という点を徹底的に追求した音楽であるから、少なくとも演奏の背後に流れるコードを感じながら聴けなければ、この音楽を聴く楽しみは半減する。
そういう意味でも、モダンジャズの創始者であるパーカーの具体的な演奏の特徴を(ある程度平易に)分析した部分は、むしろ音楽理論苦手の方々に(流し読みでもいいので)是非読んでいただき、ジャズの核心にある高度に音楽的な部分を(漠然とでも)感得してほしいと思う。
パーカーの伝記やインタビュー本は、ライズナーの「チャーリー・パーカーの伝説」やラッセルの「バードは生きている」などの古典があるが、その後も関係者やミュージシャンから様々な発言が繰り返され、旧説と矛盾する説も多々あって収拾のつかない状況だったと思う。
本書の第1部では、こうした雑多な資料を適切に取捨選択し、新しい証拠も踏まえて、短いながらパーカーの人生の納得のいく素描になっていると思う。
第2部では、採譜された楽譜も多用して、年代順にパーカーのアドリブ技法の特徴を分析している。
特に、パーカーがビ・バップの根幹となる奏法を編み出し完成させていく1940年~43年は、レコーディング・ストなどの影響で音源がほぼ皆無だったが、近年発見された私家版録音などを基に、レスター・ヤング、コールマン・ホーキンス、バスター・スミス等からの影響関係を具に分析するあたりは、パーカー・ファン必読であろう。
この手の研究書としては、Thomas Owens や Henry Martin の著書(いずれも未訳)が有名だが、最近では濱瀬元彦氏の「チャーリー・パーカーの技法」という快著がある。が、これらはいずれも、楽理やコード理論をかなりのレヴェルでマスターしたミュージシャンやマニアでなければ読みこなすのは困難だろう。
このウォイデック氏の本は、楽譜を用い、コード関係の用語も頻出するが、逐次平易な言葉で要点を総括してくれているので、まったくコード理論を知らない人でもある程度ついていけるはずだ。(コードのイロハぐらいを多少知っている人なら充分読める。)
音楽を個人で楽しむのに理論や分析など関係ないという人も多いだろうが、ビ・バップ(=モダンジャズ)の最大の特徴は、アドリブの基礎として「コード進行」の概念を明確に打ち出し、そのコード進行に基づいてどこまでヴィヴィッドにかつ自由にアドリブできるか、という点を徹底的に追求した音楽であるから、少なくとも演奏の背後に流れるコードを感じながら聴けなければ、この音楽を聴く楽しみは半減する。
そういう意味でも、モダンジャズの創始者であるパーカーの具体的な演奏の特徴を(ある程度平易に)分析した部分は、むしろ音楽理論苦手の方々に(流し読みでもいいので)是非読んでいただき、ジャズの核心にある高度に音楽的な部分を(漠然とでも)感得してほしいと思う。